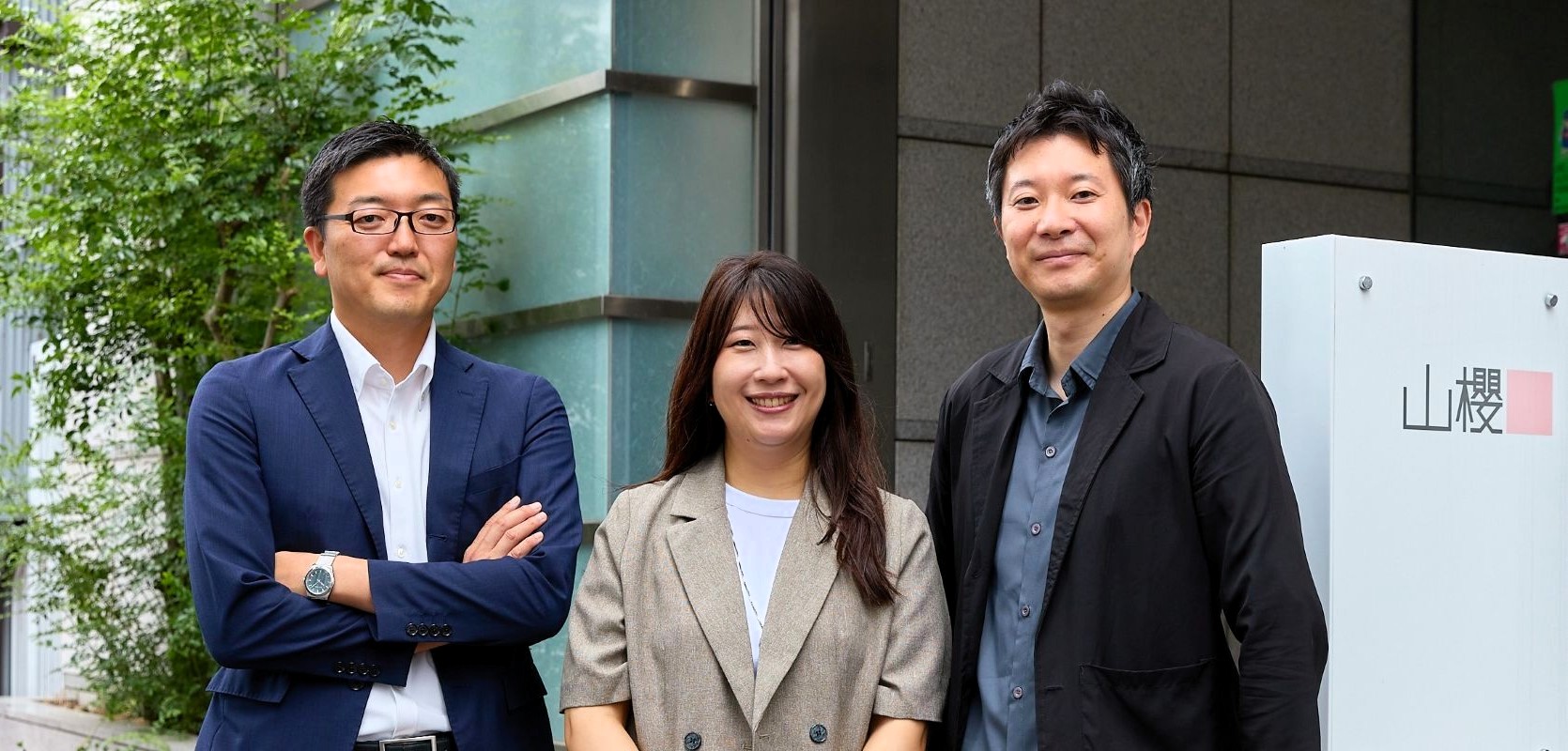ビーティス3製品を効率よく活用! ~BCP対策は新時代に合わせたスマートな対応へ~|大阪シーリング印刷株式会社 様

大阪シーリング印刷株式会社様は、長年弊社製品をご利用いただいているお客様だ。今回は、ご利用いただいているそれぞれの製品QUICK-EDD/QUICK-Justi/QUICK-Hawk_iについて活用方法などのお話を伺った。
IT推進部 部長 藤原 武志氏
副部長 若尾 武司氏
大森 良和氏
導入製品・サービス
ポイント
- ISO22301取得と会社全体でのBCP対策実施
- QUICK-Justiの意外な使い方
- 迅速なエラー対応のためのQUICK-Hawk_i
BCP(事業継続計画)対策の取り組みについて
同社は、自然災害をはじめ、システムトラブル・停電・火災といった事業継続に対する潜在的な脅威に備えて、2019年に本社を含めた3拠点を対象に、品質向上の一環として事業継続マネジメントシステム(BCMS)の国際規格ISO22301を取得した。
システム面でのBCP対策
同社は、早くからシステム面においても災害対策・障害対策に取り組んでいる。HA導入前は、前日の全データを記録したカートリッジテープを大阪本社と距離の離れた名古屋支店へ毎日送付し保管することで、前日の全データが安全に常に2か所で保管される仕組みを作り、広域災害に備えていた。本格的な災害対策を実施するためにHA(現QUICK-EDD)を導入したのは2004年。当時は、本社と九州工場でシステムの二重化をおこなっていた。2011年3月の東日本大震災の影響により関西地区でも計画停電の予定が発表されたことでシステム構成の見直しをおこなった。計画停電によってIBM iが停止すると業務への影響が大きいため、データセンターにIBM iを移設、それから現在に至るまで、東京と大阪のデータセンターを利用して災害対策をおこなっている。同社の許容停止時間は2時間と設定し、それを超えた際は、切替を行う運用ルールを策定。幸い現在まで切替を実施するような大きなトラブルは発生していない。
しかし、同社は、広域災害に対しての体制は整えているが、自社のみの障害に対しての体制は不十分と感じている。例えばハード障害やピンポイントの水害などが発生して自社だけの問題で業務が停止してしまうことは、取引先のお客様に理解を得られない部分であるため、今後は、広域だけでなく身近なところのBCP対策をとっていく必要があると強く感じている。
2020年にIBM iのリプレイスを予定。次の構成では、テスト区画を設けて、現在実施できていない切替テストも積極的に行う計画を立てている。現在に至るまで、QUICK-EDDによるバックアップ体制は問題もなく順調に運用されているが、今後、QUICK-EDDの監視を他のサーバー監視と同じ運用の中に入れ、目視でも定期的に監視していく予定だ。
QUICK-Justi アクセルログがバグ調査に活躍
同社では、QUICK-EDDだけではなく、セキュリティソフトである内部統制ツールQUICK-Justiとメッセージ監視サービスQUICK-Hawk_iもご利用いただいている。
QUICK-Justiは、2010年にログ取得を目的として導入した。はじめはログの取得として利用していたが、ある時、誤って更新してしまったレコードを更新前の元の状態にコピーで戻せることがわかった。その後はこのような活用をすることが多い。誤って削除してしまったとしても、削除前と削除後の両方のログが残っているため正確に復元ができ、復元後、慌てることなく原因解明をすることもできる。また、同社では古いプログラムも保管しているためバグ調査に役に立っている。「こうしたQUICK-Justiの使い方を皆さんは知らないと思います。古いプログラムが時代や条件が変わることで、新しいプログラムが動き始めると、矛盾がおきてしまう可能性があります。変更した値が、なぜか元に戻っているということがあるのですが、QUICK-Justiは、そのような調査にも非常に有効です。このフロアにいる全員が、QUICK-Justiを使いこなし、ログから調べて、古いバグを発見してくれます。」と大森氏は言う。「以前は、バグを修正すれば問題ありませんでした。しかし近年は、品質マネジメントシステムISO9001の観点から、品質保証部からなぜその問題が発生したのかを要求されることが増え、その調査にも非常に有効です。」(大森氏)
「以前はテープからデータを戻すなどして調査にも非常に時間がかかっていたが、簡単に調査ができるようになったおかげで原因要求の質問に対してもすぐ回答することができるようになり、負担もだいぶ軽減されました。」と藤原氏は言う。
システムが非常に複雑で、多くのプログラムでデータを更新しているためどこで問題が発生しているかわかりづらいが、データが時系列で並んでいるので非常にわかりやすい。日付検索もできるため、過去にさかのぼりたい場合は、日付ごとにメンバーを設定し、検索が簡単に行える。メンバーオールでコピー&ペーストして時系列で表示すればすぐ問題点を発見でき、誰がプログラムを変更したのか、調査することも可能だ。同社は、約30年前のAS/400時代から自社開発を行っているプログラムが多く、過去のプログラムを調査するのにも非常に役に立っている。同社は、データ量も他社に比べると多く、IBM iの活用も多い。何十年も蓄積されたデータも保管しており、現在は年間150万件以上もある受注データを10年分照会できるようにしている。「実際使用していないプログラムも棚卸をすれば数は減らせるがそこまでの整備はできていません。ただ重要ファイルは決まっているので、その検索や調査をする上でもQUICK-Justiがないと困りますね。もしかしたら、データの棚卸にもうまくQUICK-Justiが利用できるかもしれません。」(若尾氏)
「QUICK-Justiは本当に便利でとても助けられています。自社開発が非常に長く、古いプログラムもまだ動いているため、そのバグを発見できるのは非常に便利です。多くの人に使用してほしいと思っています。」(大森氏)「逆に他社さんがどのように利用しているか知りたいところですね。」と藤原氏は言う。
QUICK-Justiは、セキュリティツールとしての活用だけではなく、お客様によって様々な活用方法があるようだ。
監視メッセージで即対応可能!
同社では、クラウド型監視サービス「QUICK-Hawk_i」もご利用いただいている。こちらは、プログラムの停止、ファイル容量プログラム全般に対するエラーの監視をしている。何か問題が発生すると担当者のスマートフォンにメールが送付される仕組みだ。「以前は、コンソールを1台用意して、そこにエラーメッセージが送られてくる形だったが、今は手元のスマートフォンでメッセージに気づくのでとても便利です。手順が大胆に変わりおもしろいなと思います。」と大森氏は振り返る。「エラーに気づくのが早くなりました。他部署からプログラム停止などの指摘が来る前に対処できるようになっています。」(藤原氏)「Windows画面やホスト画面をいくつも開いているためPC側にメッセージが届いても気づかないことが多いですが、スマートフォンの通知で気づけるのでとても便利です。」(若尾氏)
同社では、メッセージの対象担当者が不在の場合でも他の社員が対応を行うなどお互いをカバーし合うことで、他部署から指摘される前にエラーに対応できるようになり、システム停止などの事前対応が可能になった。
今後の課題
同社は、IBM iだけに限らずネットワークや他のハードウェアに関しても二重化の体制をとっている。そのため何かしらに問題が発生しても二重化の仕組みがうまく動いているが故に障害に気づかないことが多く、難しいところである。その反省をもとに現在では、目視によるチェックを毎日実施している。「二重化体制により、障害が起きたことに気づきにくくなっているということは問題であり、そこをどう改善していくのかが、今後の課題でもあります。」と大森氏は言う。
また、同社は、様々な業務データをIBM iで稼働させているが、最近は、PCやスマートフォンに慣れている社員が多いため、社員全員が使いやすいように開発を行っている。
「今後IBM iだけでやっていくのは難しいので、新しい技術と一緒になっていくことが必要です。IBM iのデータとうまく連携させながら画面もタッチパネルで操作できるように開発をおこなっているところです。」と若尾氏は言う。信頼性の高いIBM iは残しつつ必要な部分は時代にあわせていくことが今後の課題とのことだ。