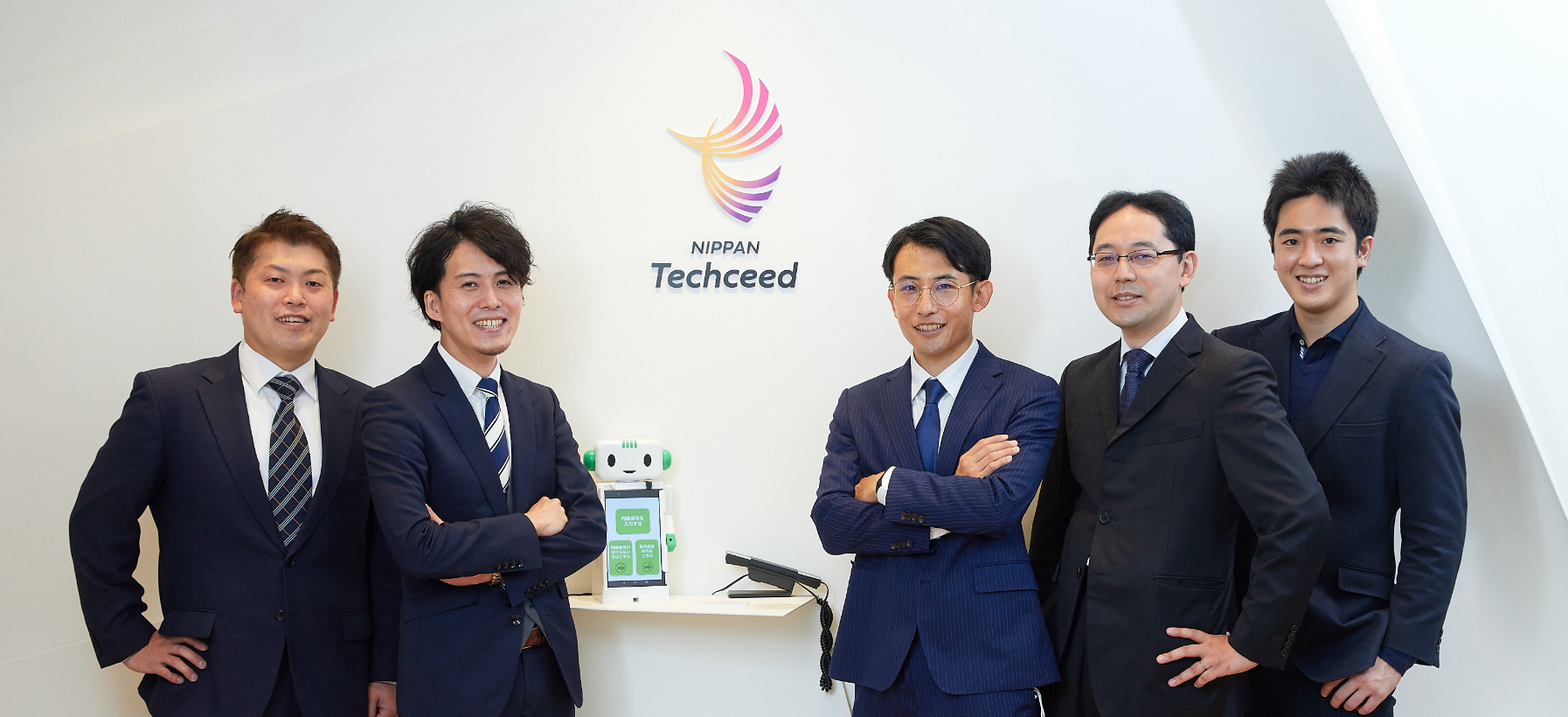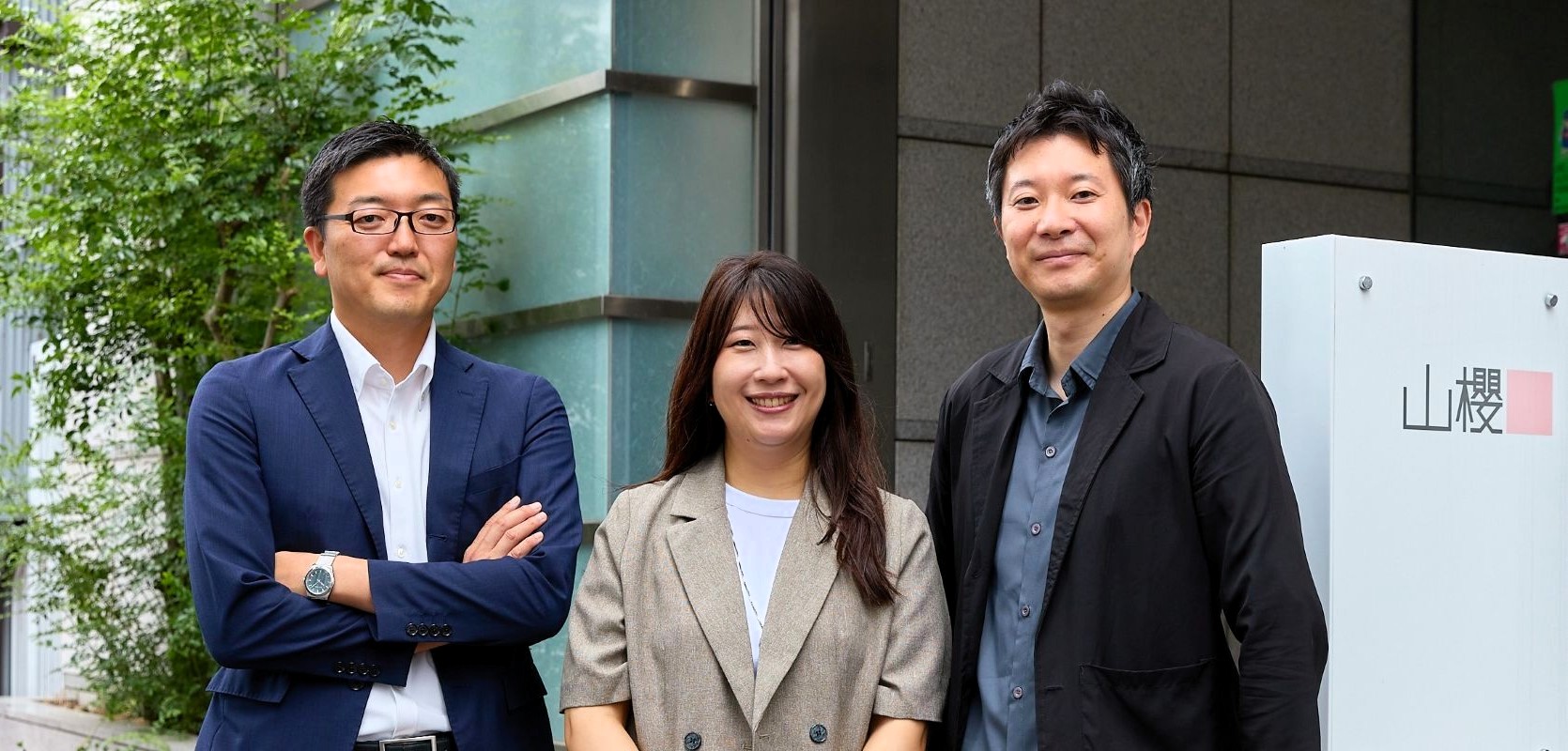百貨店が求める高度なジョブ管理をサーバ版A-AUTOで最適化|株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ様

東京都新宿区に本社を置く株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ(以下、三越伊勢丹システム・ソリューションズ)は、1968年12月に株式会社伊勢丹データーセンターとして設立された情報処理サービス企業です。2008年7月には、システム統合にともなうグループ内組織再編によって、商号を現在のものに変更。現在は、日本を代表する二つの百貨店、伊勢丹と三越に対して、システム開発から運用に至る全フェーズの情報処理サービスを24時間365日提供しています。
三越伊勢丹システム・ソリューションズとユニリタのジョブ管理ツール「A-AUTO(エーオート)」の出会いは、メインフレーム全盛期のことでした。その後、業務システムのオープン系への移行が進むにつれて、同社はサーバ版A-AUTOのライセンスも追加で購入。百貨店における幅広い業務に応じた運用管理ツールとして、日々のジョブスケジューリングとオペレーションに活用しています。
伊勢丹と三越の業務システムが完全に統合された後も、ジョブスケジューラーにはA-AUTOが引き続き使われる予定であり、更なる業務の効率化やコスト低減などに、これからも力を発揮しようとしています。
目次
導入製品・サービス
導入メリット
- 高度なジョブ管理をサーバー版A-AUTOで最適化
- リレーションによるツールへの信頼、サポート力の信頼
- A-AUTO一本化による経験/ノウハウ活用、コスト削減
- 市場ニーズや環境変化に柔軟に対応し、進化し続けるA-AUTOへの期待
百貨店の業務システムに高い処理能力を持つジョブ管理ツール「A-AUTO」を採用

株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ
共通技術部 技術第2担当
主任 槇原 朝義氏
伊勢丹と三越―。日本を代表するこの二つの百貨店に、三越伊勢丹システム・ソリューションズは24時間365日の情報処理サービスを提供しています。カバーしている領域は、システム開発から運用に至るまですべて。おもな業務システムやサービスは、基幹系システム、マーチャンダイジング(MD)システム、POSシステム、クレジットシステム、オンラインショッピングサイト、共同配送・調達システム、会計や人事システムなど多岐にわたっています。
三越伊勢丹システム・ソリューションズがユニリタのジョブ管理ツール「A-AUTO」を導入したのは、10年以上も前のこと。「百貨店には開店時間と閉店時間があり、毎日の売り上げを締めた上で、週次や月次のタイミングでさまざまなレポートを作成しています。ですから、情報処理サービスにおけるバッチジョブの占める比重は非常に高く、日々、大量のジョブネットを確実に処理するにはA-AUTOのような高い処理能力を持つジョブスケジューラーが欠かせません」(共通技術部 技術第2担当 主任 槇原朝義氏)という同社の情報システム環境によりA-AUTOが導入されました。
このような背景から、2000年ごろから始まった同社システムのオープン系への段階的な移行においても、ジョブスケジューラーは業務システムの運用に欠かせない重要なツールとして位置付けられることになりました。限られたバッチジョブを自動起動するだけなら対応できますが、一日あたり数千のジョブネットがスケジュールされる同社の情報システム環境では、ユニリタのA-AUTOのような高い処理能力を持つジョブ管理ツールが必要でした。
メインフレーム版「A-AUTO」の実績と信頼によりオープン系環境にも「A-AUTO」を採用

株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ
運用・技術統括部 共通技術部
部長 津久井 明弘氏
このような膨大な業務ニーズを満たすオープン系のジョブ管理ツールの選定には、ユニリタの「サーバ版A-AUTO」のほかにもいくつかの製品が候補にあがりました。同社では、業務システムごとにいくつかの製品を試験的に導入し、その中からメインの座にすえるジョブスケジューラーを選定することになりました。「オープン系への移行は中小規模の業務システムからはじめ、それぞれに、サーバ版のA-AUTOやその他のオープン系ジョブスケジューラーを組み込んで稼働させました。この状態でしばらく使って評価を積み重ね、中核となるジョブスケジューラーを選び出すことにしたのです」と、槇原氏は振り返ります。
最終的には、次の三つのポイントを評価して、サーバ版A-AUTOをメインのジョブスケジューラーとして採用することにしました。
まず、百貨店の業務に合っていたこと。また、メインフレーム用のジョブ管理ツールを原型とするサーバ版A-AUTOは、バッチジョブの比重が高い伊勢丹や三越の情報システム環境には最適のジョブ管理ツールでした。
そして、マネジメントの観点からは、運用管理に携わるエンジニアの教育コストを抑えられることが高く評価されました。「オープン化が進行中の弊社の場合、メインフレームとオープン系で異なるジョブ管理ツールを採用することはコスト増につながります。なによりエンジニアの教育コストが増えますし、長年にわたって培われてきた経験やノウハウを活かすこともできません。その点、メインフレーム版と同じ仕組みになっているサーバ版A-AUTOは、弊社にぴったりのジョブ管理ツールでした」と槇原氏は語ります。ジョブ管理ツールをユニリタの製品に一本化することで、ジョブスケジューリングやオペレーションのミスを減らせるという品質面の効果も期待されました。
最後に、ユニリタのサービス体制に対する大きな信頼感があります。「メインフレーム版のA-AUTOでは、親身で丁寧なサポートを受け、とても助かりました」と、槇原氏。ライセンス交換方式のような価格体系が用意されていることも、大きな魅力であったと言います。
コストと品質の両面で効果を発揮!ジョブスケジューラーを「A-AUTO」で統一も
オープン化が着々と進む現在、サーバ版A-AUTOは同社の情報システム環境を支える共通基盤の一つに位置付けられ、ほぼすべての業務システムのジョブスケジューリングに使われています。A-AUTOの基本ライセンス/リモートライセンスは業務システムごとにインストールされており、複数の業務システムのジョブネットをA-SUPERVISION(エースーパービジョン)でまとめて監視するスタイルで運用(図参照)。槇原氏は、「一つのA-SUPERVISIONが担当するA-AUTOの数が多くなるとオペレーションがしにくくなるので、業務システムの数が増えるにつれて、A-SUPERVISIONの台数も増やしています」と運用面での工夫を語ります。
オープン系の側でもA-AUTOをメインのジョブスケジューラーに採用したことにより、さまざまなメリットを手にすることができました。「イニシャルコストとランニングコストの両面で、コスト低減への貢献が顕著でした。ジョブスケジュールの考え方やジョブデータの登録の仕方はメインフレーム版と変わらない点や、様々なシステムが稼働している環境にも対応できるのが有効です」と語り、「今後は、A-SUPERVISIONの台数を最適化することによって、オペレータの負荷を低減していきたい」(運用・技術統括部 共通技術部 部長 津久井明弘氏)と考えています。
さらに、伊勢丹と三越の業務システムを完全に統合させるためのプロジェクトが進められている現在、サーバ版A-AUTOには新しい役割も与えられようとしています。
「完全統合後の共通基盤ではサーバを仮想化し、運用監視やバックアップの統一も考えています。ジョブスケジューラーも統一の対象になっており、完全統合後は伊勢丹のジョブも三越のジョブもサーバ版A-AUTOでコントロールする予定です」と、津久井氏。
今後も市場ニーズや環境変化に柔軟に対応し、進化し続けるA-AUTOはこれからも幅広いお客様のさまざまなシステムで力を発揮しようとしています。
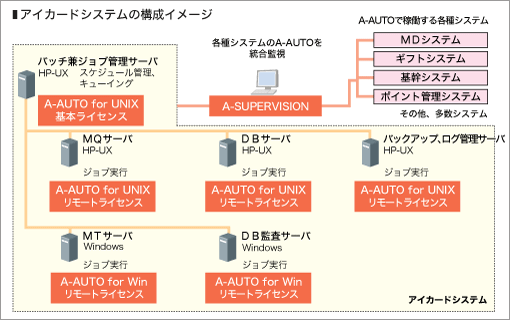
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ
- 事業内容 : 伊勢丹および三越に対して24時間365日の情報処理サービスを提供。おもな業務システム/サービスは、基幹系システム、マーチャンダイジング(MD)システム、顧客商品分析システム、POSシステム、クレジットシステム、IQRS.net(Web EDIサービス)、オンラインショッピングサイト、ギフトシステム、共同配送・調達システム、会計・人事システムなど
- 設立 : 1968年12月20日(株式会社伊勢丹データーセンター)
- ホームページ : http://www.ims-sol.co.jp/